航空局標準マニュアルの改正が、2025年3月31日付でありました。2022年12月5日の改正航空法施行日に行われた改正以来のことです。このページでは、今回の改正のポイントについてお話ししていきたいと思います。
また、ページの最後に、航空局標準マニュアル改正に伴う変更申請の必要性について紹介しております。
航空局標準マニュアルの主な改正ポイント
航空局標準マニュアルは以下のとおり6種類ありますが、2025年3月31日付で、これらのマニュアルが改正されました。
(クリックすると国土交通省ウェブサイトに掲載されている該当のマニュアルに遷移します。)
なお、国土交通省のウェブサイトに掲載されている新しいマニュアルは、改正箇所にアンダーラインが付されています。
以下では、使用頻度が多いと思われる、場所を特定しない申請で使用する「航空局標準マニュアル02」と、場所を特定した申請で使用する「航空局標準マニュアル01」について、その主な改正ポイントをご紹介いたします。
航空局標準マニュアル02の主な改正ポイント
まずは、場所を特定しない、いわゆる包括許可・承認申請で使用する航空局標準マニュアル02からご紹介いたします。
5m/s以上の突風が発生した場合でも飛行可能な条件を、ただし書きで加えた
改正前は、5m/s以上の突風が発生した場合は、即時に飛行を中止することとなっていました。これにただし書きを加えて、「製造者等が定める取扱説明書等にて確認している場合は、その条件による」ことも可能となりました。
これは、既に審査要領には記載があった「取扱説明書等に記載された風速以上の突風が発生するなど、無人航空機を安全に飛行させることができなくなるような不測の事態が発生した場合には即時に飛行を中止すること。」に平仄を合わせたものと考えられます。
物件のつり下げ又は曳航は行わないこととなっていたが、行う場合を想定したものになった
「飛行距離及び高度の限界値を設定して不必要な飛行を行わないようにし、突風や電波障害等の不測の事態を考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う」ことが示され、つり下げや曳航を行う場合も想定したマニュアルとなりました。
審査要領では、「業務上の理由等によりやむを得ずこれらの行為を行う場合には、必要な安全上の措置を講じること」とされていますが、より具体的に踏み込んだ記載となっています。
許可・承認書の携行は、電子データの携帯でも可であると明記された
オンラインシステムのDIPS2.0で許可書が発行されているので、適切な記載だと思います。
なお、国土交通省ウェブサイトの「【飛行許可承認/事故等報告】よくある質問」において、従前から以下の掲載がなされています。
Q 電子許可書の場合、どのように「許可書又はその写しの携行」を行えばよいですか?
印刷した「鑑文書」及び「許可書」(別紙がある場合には別紙も含む)を携行するか、または zipファイルに保存されたデータそのものを電子的に携行してください。
データとして携行する場合には、行政機関から問われた際に、常に視覚的に提示できるようにしてください。
雨では飛行させないこととなっていたが、飛行できる機体の扱いが示された
改正前は、「雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。」だけでした。今回の改正で「ただし、雨でも飛行可能であることを、製造者等が定める取扱説明書等にて確認している場合はその限りではない」として、例外の機体があることが示されました。
夜間飛行で、「飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況」の文言が削除された
個人的には、大きな変更と思うのがこの箇所です。
改正前は、「飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する。」との文言がありましたが、これが削除されました。
代わって、「日中、飛行させようとする経路及びその周辺の障害物件等を事前に確認し、適切な飛行経路を選定する。」が加わりました。
航空局標準マニュアル01の主な改正ポイント
次に、場所を特定した申請で使用する航空局標準マニュアル01についてご紹介いたします。
02における主な改正ポイントと同様の改正が適用された
01の場合も、上記の02でご紹介した改正は行われています。
その上で、次からは02にはなかった改正ポイントを列挙します。
目視外飛行における操縦訓練を「補助者あり」と「補助者なし」の2通りにした
改正前は、補助者なしの目視外飛行について記載はありませんでしたが、追加されました。
これは、既に審査要領には記載があった「遠隔からの異常状態の把握、状況に応じた適切な判断及びこれに基づく操作等に関し、座学・実技による教育訓練を少なくとも10時間以上受ける。」を掲載したものです。補助者を配置せず、立ち入りを制限する区画も設けない場合は、必要となる要件です。
これまで、航空局標準マニュアル01にはなかった「学校~」「高速道路~」などが加わった
これまで航空局標準マニュアル02には記載があって、01には記載がなかった「第三者の往来が多い学校、病院~」や「高速道路、交通量が多い一般道~」などの文言が、記載ぶりは異なりますが初めて加わりました。
場所を特定した個別申請の審査における実態を踏まえて、記載すべきとしたのかどうか、当局ではないので正確には分かりかねます。
また、02とは明らかに異なる箇所もあります。以下のとおりです。
鉄道上を飛行する場合については、高速道路や交通量が多い一般道と分けて記載した
鉄道上を飛行する場合はその管理者等と調整し、その指示に従い安全が確認できた場合のみとする。万が一車両又は歩行者が飛行範囲に接近又は進入した場合には直ちに飛行を中止する措置をとる。
高速道路、交通量が多い一般道やその付近については、「飛行させない」との記載であり、鉄道と扱いが異なります。
02では、鉄道も不可で「高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近では飛行させない。」です。
水上を飛行する場合を記載した
水上を飛行する場合は、船舶及び遊泳者等の進入が無いことを確認できた場合のみとし、万が一船舶又は遊泳者等が飛行範囲に接近又は進入した場合には直ちに飛行を中止する等の措置をとる。
一般道上空を飛行する場合を記載した
一般道上空を飛行する場合は、車両及び歩行者の通行がないことを確認できた場合のみとし、万が一車両又は歩行者が飛行範囲に接近又は進入した場合には直ちに飛行を中止する措置をとる。
「交通量の多い一般道」とは別の記載ですのでご注意ください。
催し場所の上空における飛行で、プロペラガードを装備できない場合の措置などが追加された
プロペラガードを装備できない場合の措置が追加された
改正前は、「飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる。」のみであったもののうしろに、「装備できない場合」の措置が追加されました。
催し場所の上空飛行の一つにドローンショーがあります。ドローンショーで使用している機体はプロペラガードを装備していないものが多いように見受けられます。
危険物の輸送と物件投下は行わないことが追加された
催し場所の上空の飛行において、これまで記載がなかった「危険物の輸送又は物件の投下は行わない。」との文言が追加されました。
以上、2025年3月31日付で改正された航空局標準マニュアルの主な改正ポイントを、2つのマニュアルを例に挙げて見て参りました。
航空局標準マニュアル改正に伴う変更申請の必要性について
さて、航空局標準マニュアルが改正されたため、変更申請をする必要があるのか?独自マニュアルの場合はどうすればいいのか?について疑問を持たれる方がいらっしゃるかもしれません。
それについては、以下に記載のページで説明しております。
このウェブサイトに掲載している情報の正確性には細心の注意を払っております。しかしながら法令解釈や制度改正等で不正確な表記を含む場合があり得ます。掲載情報を用いた行為によって生じた損害には一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
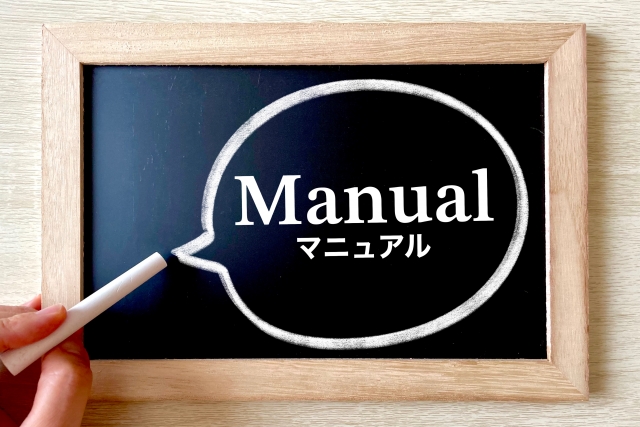
行政書士さいれんじ事務所はドローン飛行許可申請を代行しています。
ドローン飛行について、社内で航空法の義務内容の浸透が難しいことがあります。当事務所では、ドローン飛行における法令遵守の勉強会にお邪魔してお話しをさせていただいております。このページに記載しました内容でご不明なところがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
事務所概要や営業時間、代表プロフィールは「事務所の概要」をご覧ください。


