改正箇所はどこか?新旧の違いを明示します。
「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」は、航空法で規定されている無人航空機を飛行させる場合のさまざまな規制を、法律では詳細に触れていない実務・運用面の具体的な解釈が示されています。
2024年6月10日付でこの解釈文書が多岐に亘り改正されました。
本ページでは、専ら2024年6月10日付の改正点を詳しくご紹介するとともに、ページの最後に、その後の改正箇所も追記した新旧対照表を掲載しております。
その後の改正箇所とは、次のとおりです。
【2024年11月29日付改正】
「8.捜索、救助等のための特例」への追記
これは、捜索・救助の特例で、大規模災害発生時の生活必需品の輸送や防犯対策などでの飛行が該当するものであるとして、具体的に追記されたものです。国や自治体およびそれらから依頼を受けた者による飛行の特例のことです。
【2025年3月28日付改正】
「3.航空法第 132条の 86関係【飛行の方法】(6)」への追記
多数機同時運航についての追記です。同日付で公表された「多数機同時運航を安全に行うためのガイドライン」を参考にして、安全の確保を自主的に行う必要がある旨が追記されたものです。
新旧対照表は、国土交通省ウェブサイト上では改正前のものがないので調べようがないと思われた方に、これをご覧いただき参考にしていただければと思います。
「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」の掲載場所
そもそも国土交通省のウェブサイトでは、この資料がどこにあるのか見つけにくかったと思います。
2024年6月以降は、ドローンユーザーにとってはおなじみの「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」のページトップに「主なトピックス」として掲載されています。
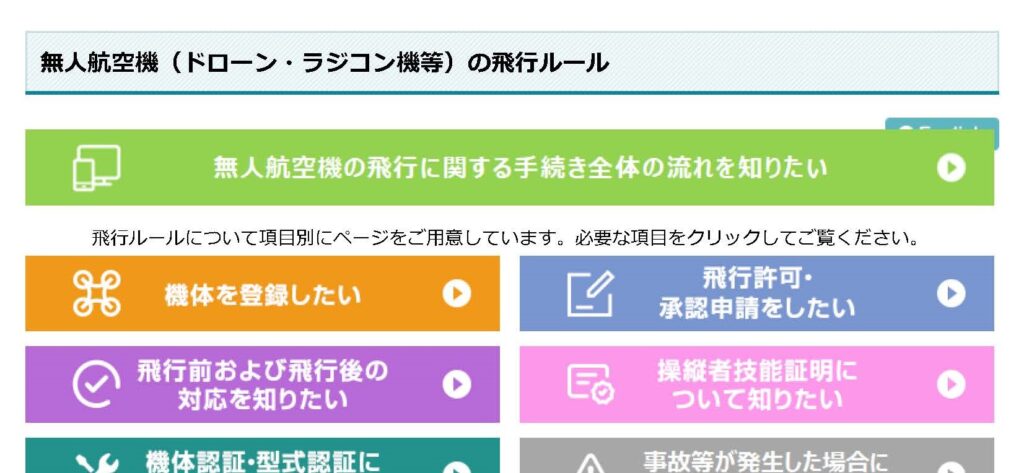
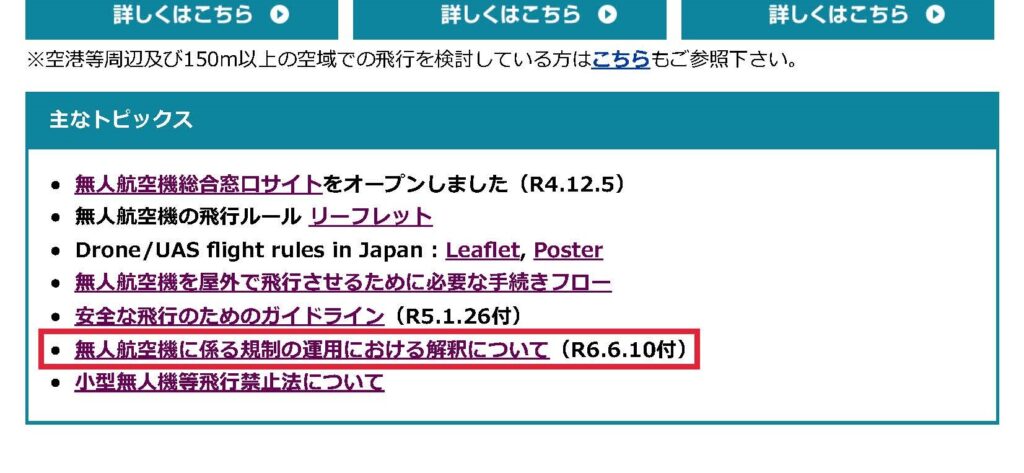
国土交通省ウェブサイトに掲載されている資料:「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」(クリックすると別ウインドウに遷移します)。
2024年6月に改正された箇所の紹介
全体を通した用語の変更
細かなことですが、解釈文書で随所に使用されていた「無人航空機を飛行させる者」が「操縦者」に用語変更されています。
飛行前の経路下の確認
飛行前に空域や周囲の状況を確認することになっていますが、「飛行経路下に第三者がいないことの確認」とのみ記載されていたものが、「飛行経路直下及びその周辺の落下分散範囲に第三者がいないことを確認」すべきと詳細に明記されました。
直下だけでは足りず、周辺の落下分散範囲までが飛行経路下であるとのこと。
2023年9月12日に開催された「カテゴリーⅡ(レベル3) 飛行の許可・承認申請に関する説明会」で、国交省から以下の資料が示されていました。「飛行経路下」についての解釈もこの説明会の質疑応答で国交省が回答しています。
※リンクを貼った↑上の説明会の資料の後半は質疑応答の議事録がついていますので宜しければご確認ください。
飛行の許可・承認申請に関する説明会資料(当日の質疑応答を含む)-1024x768.jpg)
飛行前の風速の確認
また、飛行前の気象の確認に関しては、「風速が運用限界の範囲内であることの確認」だったものが、「離着陸場所の地上風及び飛行経路上の各高度帯における風向風速変動を確認すること」と明記されています。
「風速の確認」は、風速計で離着陸場所の地上風を確認するだけでなく、飛行させる高度の風向き、風速の変動を確認するということです。
飛行高度での風向風速は、機体・制御装置やモニターによって把握できるものもありますが、把握できないものもあります。
しかし、ここで大事なことは、飛行高度での風向風速を機体・制御装置やモニターによって把握できるものであっても、「飛行前」にこの確認を行うことが必要だということです。
この「風速の確認」は、「飛行に必要な準備が整っていることの確認」についてのことです。
風速の確認については以下のページをご参照ください。
目視内飛行の定義
目視内、目視外については従前から記載されていますが、特に目視の範囲について、より具体的に示されました。
安全な飛行を行うためにバッテリー残量を確認する目的等でドローンから一時的に目を離し、モニターを確認する等は目視飛行の範囲内であると明記されています。
これは2023年9月12日に開催された「カテゴリーⅡ(レベル3) 飛行の許可・承認申請に関する説明会」での質疑応答で国交省が回答した内容が、この解釈資料でも再掲されたものです。
説明会での質疑応答では、目視外についても補足されています。
質問
目視外の定義について、モニターを確認するため機体から目を離した場合は目視外となるのか。
回答
目視内での飛行にあたっては、操縦者が機体及びその周囲の状況を目視により確認することが必要となりますが、安全飛行するためにバッテリー残量を確認する程度のモニターの確認は目視内の範疇であると認識しております。ただし、モニターを凝視する等により、機体から目を離した場合は目視外となります。
この目視外の箇所については、今回の解釈文書では、従前の「モニターを活用して見ること」から「飛行状況を専らモニターを用いて見ること」に修正されました。
イベント上空の飛行の詳述
想定して いない多数の者の集合する催しが開催されることが判明し、第三者の立ち入りやその可能性がある場合の措置が追記されました。飛行の停止や、飛行経路の変更などの必要な措置を講じることとされています。
イベント(催し)の具体例も従前よりも増えました。ドローンショー、花火大会、マラソン、街頭パレード、選挙等における屋外演説会が追記されました。
また、直接・間接的に関与する人のみの参加で行うイベントは該当しないことも追記となっています。
物件投下への追記
「対象物件を地表等に落下させることなく地上の人員に受け渡す行為」は物件投下に当たらないことが明記されました。
物資配送などの実態に合わせて記載されたものと思います。
立入管理措置への追記
立入管理区画の設定に当たって、飛行させるドローンの「落下分散範囲も考慮しなければならない」ことが追記となっています。
また、審査要領に基づき、機体に取り付けられた「カメラを活用して補助者を配置せずに目視外飛行を行う場合、カメラによる第三者の立ち入り確認をもって、立入管理措置が行われたものとみなす」ことが追加されています。これはレベル3.5飛行のことです。
2023年12月26日付改正、同年12月27日に国交省ウェブサイトに掲載された「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」において、レベル3.5飛行の場合は、機体に取り付けられたカメラにより第三者の立ち入りが無いことを確認することで立入管理措置とみなされることとなりました。
この「みなす」解釈は航空法上で重要です。
航空法第132条の85において、「立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。」とされています。
航空法を改正することなく、つまり条文との整合性をとるためには、カテゴリーⅢではないレベル3.5飛行は、立入管理措置が行われていなければならないからです。
間接関与者の例示
第三者に該当しない間接関与者の例示が行われています。
「映画の空撮における俳優やスタッフ、学校等での人文字の空撮における生徒等」と記載されました。
第三者上空の解釈の新設
これは解釈文書に新たに設けられたものです。
前述の「カテゴリーⅡ(レベル3)飛行の許可・承認に関する説明会」における質疑応答での国交省回答や、「レベル3.5創設」を踏まえて明文化したものと思います。
第三者上空には「第三者が乗り込んでいる移動中の車両等の上空を含む」と記載されました。
また、「上空」とはドローンの「落下距離(飛行範囲の外周から製造者等が保証した落下距離)を踏まえ、落下する可能性のある領域に第三者が存在する場合」は、「第三者の上空であるものとみなす」と記載されています。
他方、第三者上空にあるとはみなさないものも明記されています。
「第三者が遮蔽物に覆われ」ており、ドローンが「衝突しても遮蔽物で第三者が保護されている場合(第三者が屋内や停止中の車両等の内部にある場合等。)
第三者が移動中の車両等(ドローンが衝突しても遮蔽物で第三者が保護される状態にある場合に限る。)の中にある場合であって、レベル3.5飛行として一時的に当該移動中の車両等の上空を飛行するとき。
ただし、遮蔽物に覆われず、保護されない状況になった場合は対象外。人が車両から出てきた場合やバイク運転は対象外です。
レベル3.5飛行では、ドローンが一時的に移動中の車両等の上空を横断する場合(遮蔽物に覆われず、保護されない状況になった場合を除き)、特定飛行中のドローンの下に人の立入又はそのおそれのあることを確認したときに該当しないとしています。
補助者についての追記
補助者の役割として、ドローンの「飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視すること」が付け加えられています。
捜索・救助の特例への追記
航空法132条の92は捜索・救助の特例について規定されています。これに関して「緊急性がある飛行」が対象であると追記されました。
緊急性は、「飛行の許可・承認申請の対応窓口への申請を行う手段又はいとまがない状況」を指すものであることが補足されています。
航空法132条の92の特例の該当者は、国・地方公共団体または国・地方公共団体の依頼により捜索又は救助を行う者です。
「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」の新旧対照表
さて、それでは新旧対照表にしてご紹介します。「改正後」の欄のうち朱書きにしたところが2024年(令和6年)6月10日付で変更・追記された改正箇所です。
なお、2024年(令和6年)11月29日付の追記箇所は、青字で追加いたしました。
更に、2025年(令和7年)3月28日付の追記箇所は、緑色で追加いたしました。
新旧対照表は膨大なボリュームですので、スマホの方は読みにくいと思います。できればPCやタブレット端末でご覧いただくことをお勧めいたします。
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| 平成 27 年 11 月 17 日 制定 (国空航第 690 号、国空機第 930 号) 令和6年6月 10 日 最終改正(国空無機第 19380 号) 令和6年11月29日 最終改正(国空無機第68755号) 令和7年3月28日 最終改正(国空無機第103905号) | 平成 27 年 11 月 17 日 制定 (国空航第 690 号、国空機第 930 号) 令和5年1月 26 日 最終改正(国空無機第 262271 号) |
| 航空局安全部無人航空機安全課長 無人航空機に係る規制の運用における解釈について | 航空局安全部無人航空機安全課長 無人航空機に係る規制の運用における解釈について |
| 1.航空法第2条第 22 項関係 (1)無人航空機 航空法の一部を改正する法律(平成 27 年9月 11 日法律第 67 号)により、次のとおり、「無人航空機」の定義が新たに追加された。 | 1.航空法第2条第 22 項関係 (1)無人航空機 航空法の一部を改正する法律(平成 27 年9月 11 日法律第 67 号)により、次のとおり、「無人航空機」の定義が新たに追加された。 |
| 無人航空機:航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器(※)であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。 ※現在、政令で定める機器はない。 | 無人航空機:航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器(※)であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。 ※現在、政令で定める機器はない。 |
| ここで、上記の解釈は次のとおりである。 ○「構造上人が乗ることができないもの」とは、当該機器の概括的な大きさや潜在的な能力を含めた構造、性能等を確認することにより、これに該当すると判断されたものをいう。 ○「遠隔操作」とは、プロポ等の操縦装置を活用し、空中での上昇、ホバリング、水平飛行、下降等の操作を行うことをいう。 ○「自動操縦」とは、当該機器に組み込まれたプログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。具体的には、事前に設定した飛行経路に沿って飛行させることができるものや、飛行途中に人が操作介入することができず離陸から着陸まで完全に自律的に飛行するものが存在する。 | ここで、上記の解釈は次のとおりである。 ○「構造上人が乗ることができないもの」とは、当該機器の概括的な大きさや潜在的な能力を含めた構造、性能等を確認することにより、これに該当すると判断されたものをいう。 ○「遠隔操作」とは、プロポ等の操縦装置を活用し、空中での上昇、ホバリング、水平飛行、下降等の操作を行うことをいう。 ○「自動操縦」とは、当該機器に組み込まれたプログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。具体的には、事前に設定した飛行経路に沿って飛行させることができるものや、飛行途中に人が操作介入することができず離陸から着陸まで完全に自律的に飛行するものが存在する。 |
| (2)無人航空機から除かれるもの 航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして、航空法施行規則第5条の2により、重量が 100 グラム未満のものは無人航空機の対象からは除外される。 ここで、「重量」とは、無人航空機本体の重量及びバッテリーの重量の合計を指しており、バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まないものとする。 | (2)無人航空機から除かれるもの 航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして、航空法施行規則第5条の2により、重量が 100 グラム未満のものは無人航空機の対象からは除外される。 ここで、「重量」とは、無人航空機本体の重量及びバッテリーの重量の合計を指しており、バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まないものとする。 |
| 2.航空法第 132 条の 85 関係【飛行の禁止空域】 (1)人又は家屋の密集している地域(以下「人口集中地区」という。)においては、無人航空機の不具合等による落下により、地上及び水上の人及び物件に対して危害を及ぼす蓋然性が高くなることから、航空法第 132 条の 85 第1項第2号により、この地域の上空における無人航空機の飛行を禁止するものである。 ただし、人口集中地区内であっても、地域の実情や無人航空機に対する様々なニーズがあることを踏まえ、地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合には、国土交通大臣が告示で定める地域(※)については、人又は家屋の密集している地域から除外する。 なお、人口集中地区内の私有地内における飛行であっても、強風等により予期せぬ場所に飛ばされることも想定されるため、人口集中地区内である限り、飛行の禁止空域に該当する。 ※現在、人又は家屋の密集している地域から除外する地域として告示で定める地域はない。 | 2.航空法第 132 条の 85 関係【飛行の禁止空域】 (1)人又は家屋の密集している地域(以下「人口集中地区」という。)においては、無人航空機の不具合等による落下により、地上及び水上の人及び物件に対して危害を及ぼす蓋然性が高くなることから、航空法第 132 条の 85 第1項第2号により、この地域の上空における無人航空機の飛行を禁止するものである。 ただし、人口集中地区内であっても、地域の実情や無人航空機に対する様々なニーズがあることを踏まえ、地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合には、国土交通大臣が告示で定める地域(※)については、人又は家屋の密集している地域から除外する。 なお、人口集中地区内の私有地内における飛行であっても、強風等により予期せぬ場所に飛ばされることも想定されるため、人口集中地区内である限り、飛行の禁止空域に該当する。 ※現在、人又は家屋の密集している地域から除外する地域として告示で定める地域はない。 |
| (2)地表又は水面から 150m以上の高さの飛行の禁止空域から、地上又は水上の物件から 30m以内の空域が除外される。例えば、空港等の周辺、緊急用務空域又は人口集中地区のいずれにも該当しない地域において、高層の建物の壁や屋上から 30 メートル以内の空域であれば、150 メートル以上の高さの空域に達する場合であっても、無人航空機を無許可で飛行させることが可能となる。したがって、当該物件から 30m以内の空域の飛行を行う際には、本除外規定に基づく当該物件の関係者による飛行、若しくは、航空法第 132 条の 86 第2項第3号に掲げる方法(第三者から 30mの距離を保つこと)によらずに飛行を行うことについて同条第3項又は第5項第2号の承認を受けた飛行のいずれかとなる。 また、高構造物をつなぐ送電線等も物件にあたることから、当該送電線等から 30m以内の空域についても除外される。 なお、対象物件については、150m以上に限定していないことから、物件から 30m以内に地表又は水面から 150m以上の高さの飛行の禁止空域がある場合には、当該空域は除外される。 当該空域が人口集中地区の上空にあたる場合には、航空法第 132 条の 85 第1項第2号の飛行にかかる許可は必要である。 | (2)地表又は水面から 150m以上の高さの飛行の禁止空域から、地上又は水上の物件から 30m以内の空域が除外される。例えば、空港等の周辺、緊急用務空域又は人口集中地区のいずれにも該当しない地域において、高層の建物の壁や屋上から 30 メートル以内の空域であれば、150 メートル以上の高さの空域に達する場合であっても、無人航空機を無許可で飛行させることが可能となる。したがって、当該物件から 30m以内の空域の飛行を行う際には、本除外規定に基づく当該物件の関係者による飛行、若しくは、航空法第 132 条の 86 第2項第3号に掲げる方法(第三者から 30mの距離を保つこと)によらずに飛行を行うことについて同条第3項又は第5項第2号の承認を受けた飛行のいずれかとなる。 また、高構造物をつなぐ送電線等も物件にあたることから、当該送電線等から 30m以内の空域についても除外される。 なお、対象物件については、150m以上に限定していないことから、物件から 30m以内に地表又は水面から 150m以上の高さの飛行の禁止空域がある場合には、当該空域は除外される。 当該空域が人口集中地区の上空にあたる場合には、航空法第 132 条の 85 第1項第2号の飛行にかかる許可は必要である。 |
| 3.航空法第 132 条の 86 関係【飛行の方法】 (1)アルコール等の影響により正常な飛行ができないおそれがある間の飛行禁止 アルコール等の摂取時には注意力や判断力が低下し、無人航空機の正常な飛行に影響を与えるおそれがあることから、航空法第 132 条の 86 第 1 項第1号により、アルコール又は薬物の影響により正常な飛行ができないおそれがある間の飛行を禁止している。 ここで、「アルコール」とは、アルコール飲料やアルコールを含む食べ物をいうものとする。 アルコールによる身体への影響は、個人の体質やその日の体調により異なるため、体内に保有するアルコールが微量であっても無人航空機の正常な飛行に影響を与えるおそれがある。このため、体内に保有するアルコール濃度の程度にかかわらず体内にアルコールを保有する状態では無人航空機の飛行を行わないこと。 また、「薬物」とは、麻薬や覚醒剤等の規制薬物に限らず、医薬品も含まれるものとする。 さらに、航空法第 132 条の 86 第 1 項第1号の規定に違反して、公共の場所において無人航空機を飛行させた場合には1年以下の懲役又は 30 万円以下の罰金が科されるところ、ここで「公共の場所」とは、公衆すなわち不特定多数の者が自由に利用し又は出入りすることができる場所をいい、道路、公園、広場、駅等がこれに含まれ得る。 | 3.航空法第 132 条の 86 関係【飛行の方法】 (1)アルコール等の影響により正常な飛行ができないおそれがある間の飛行禁止 アルコール等の摂取時には注意力や判断力が低下し、無人航空機の正常な飛行に影響を与えるおそれがあることから、航空法第 132 条の 86 第 1 項第1号により、アルコール又は薬物の影響により正常な飛行ができないおそれがある間の飛行を禁止している。 ここで、「アルコール」とは、アルコール飲料やアルコールを含む食べ物をいうものとする。 アルコールによる身体への影響は、個人の体質やその日の体調により異なるため、体内に保有するアルコールが微量であっても無人航空機の正常な飛行に影響を与えるおそれがある。このため、体内に保有するアルコール濃度の程度にかかわらず体内にアルコールを保有する状態では無人航空機の飛行を行わないこと。 また、「薬物」とは、麻薬や覚醒剤等の規制薬物に限らず、医薬品も含まれるものとする。 さらに、航空法第 132 条の 86 第 1 項第1号の規定に違反して、公共の場所において無人航空機を飛行させた場合には1年以下の懲役又は 30 万円以下の罰金が科されるところ、ここで「公共の場所」とは、公衆すなわち不特定多数の者が自由に利用し又は出入りすることができる場所をいい、道路、公園、広場、駅等がこれに含まれ得る。 |
| (2)飛行に必要な準備が整っていることを確認した後の飛行 飛行前に機体の点検等を実施することで故障等による落下を防止するため、航空法第 132 条の 86 第 1 項第2号により、飛行に必要な準備が整っていることを確認した後において飛行させることとしている。また、航空法施行規則第 236 条の 77 に定められた確認しなければならない事項とその具体的な例は次の通りである。 ① 当該無人航空機について、航空法施行規則第 236 条の 75 で求められる外部点検及び作動点検などの日常点検を実施し、「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」(令和 4年 12 月1日付国空無機第 236963 号)の日常点検記録に記録すること。なお、リモート ID 機能を有する機器等の取外し可能な付属品を含め日常点検の内容や頻度について設計者の取扱説明書等により指定されている場合は、これに従うこと。 | (2)飛行に必要な準備が整っていることを確認した後の飛行 飛行前に機体の点検等を実施することで故障等による落下を防止するため、航空法第 132 条の 86 第 1 項第2号により、飛行に必要な準備が整っていることを確認した後において飛行させることとしている。また、航空法施行規則第 236 条の 77 に定められた確認しなければならない事項とその具体的な例は次の通りである。 ① 当該無人航空機について、航空法施行規則第 236 条の 75 で求められる外部点検及び作動点検などの日常点検を実施し、「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」(令和 4年 12 月1日付国空無機第 236963 号)の日常点検記録に記録すること。なお、リモート ID 機能を有する機器等の取外し可能な付属品を含め日常点検の内容や頻度について設計者の取扱説明書等により指定されている場合は、これに従うこと。 |
| ② 当該無人航空機を飛行させる空域及びその周囲の状況を確認すること 具体的な例:飛行経路に航空機や他の無人航空機が飛行していないことの確認 飛行経路の直下及びその周辺の落下分散範囲に第三者がいないことの確認 | ② 当該無人航空機を飛行させる空域及びその周囲の状況を確認すること 具体的な例:飛行経路に航空機や他の無人航空機が飛行していないことの確認 飛行経路下に第三者がいないことの確認 |
| ③ 当該飛行に必要な気象情報を確認すること 具体的な例:風速が運用限界の範囲内であることの確認 風速においては、離着陸場所の地上風及び飛行経路上の各高度帯における風向風速変動を確認すること 気温が運用限界の範囲内であることの確認 降雨量が運用限界の範囲内であることの確認 十分な視程が確保されていることの確認 | ③ 当該飛行に必要な気象情報を確認すること 具体的な例:風速が運用限界の範囲内であることの確認 気温が運用限界の範囲内であることの確認 降雨量が運用限界の範囲内であることの確認 十分な視程が確保されていることの確認 |
| ④ 燃料の搭載量又はバッテリーの残量を確認すること 具体的な例:十分な燃料又はバッテリー残量を有していることの確認 | ④ 燃料の搭載量又はバッテリーの残量を確認すること 具体的な例:十分な燃料又はバッテリー残量を有していることの確認 |
| (3)航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するための方法による飛行 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、航空法第 132 条の 86 第 1 項第3号により、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させる等の方法により飛行させることとしている。また、航空法施行規則第 236 条の 78 に定められた衝突を予防するための方法とその具体的な例は次の通りである。 ① 無人航空機を飛行させる者(以下「操縦者」という。)は、無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の航空機を確認し、衝突のおそれがあると判断される場合は、当該無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じることとする。 ② 操縦者は、無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の他の無人航空機を確認したときは、他の無人航空機との間に安全な間隔を確保して飛行させること、又は衝突のおそれがあると判断される場合は、無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じることとする。 ここで、「その他適当な方法を講じること」とは、衝突する可能性のある方向とは別の方向に無人航空機を飛行させることをいい、空中で停止することも含まれ得る。 | (3)航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するための方法による飛行 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、航空法第 132 条の 86 第 1 項第3号により、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させる等の方法により飛行させることとしている。また、航空法施行規則第 236 条の 78 に定められた衝突を予防するための方法とその具体的な例は次の通りである。 ① 無人航空機を飛行させる者は、無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の航空機を確認し、衝突のおそれがあると判断される場合は、当該無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じることとする。 ② 無人航空機を飛行させる者は、無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の他の無人航空機を確認したときは、他の無人航空機との間に安全な間隔を確保して飛行させること、又は衝突のおそれがあると判断される場合は、無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じることとする。 ここで、「回避させること」とは、衝突する可能性のある方向とは別の方向に無人航空機を飛行させることをいい、空中で停止することも含まれ得る。 |
| (4)他人に迷惑を及ぼすような方法での飛行禁止 不必要に騒音を発したり急降下させたりする行為は、周囲に不快感を与えるだけでなく、危険を伴うこともあることから、航空法第 132 条の 86 第 1 項第4号により、他人に迷惑を及ぼすような方法での飛行を禁止している。 ここで、航空法第 132 条の 86 第 1 項第4号の規定は、危険な飛行により航空機の航行の安全や地上の人や物件の安全が損なわれること防止することが趣旨であることから、「他人に迷惑を及ぼすような方法」とは、人に向かって無人航空機を急接近させることなどをいうものとする。 | (4)他人に迷惑を及ぼすような方法での飛行禁止 不必要に騒音を発したり急降下させたりする行為は、周囲に不快感を与えるだけでなく、危険を伴うこともあることから、航空法第 132 条の 86 第 1 項第4号により、他人に迷惑を及ぼすような方法での飛行を禁止している。 ここで、航空法第 132 条の 86 第 1 項第4号の規定は、危険な飛行により航空機の航行の安全や地上の人や物件の安全が損なわれること防止することが趣旨であることから、「他人に迷惑を及ぼすような方法」とは、人に向かって無人航空機を急接近させることなどをいうものとする。 |
| (5)昼間(日中)における飛行 夜間では、無人航空機の位置や姿勢だけでなく、周囲の障害物等の把握が困難になり、無人航空機の適切な制御ができず墜落等に至るおそれが高まることから、航空法第 132 条の 86 第2項第1号により、昼間(日中)」のみ(日出から日没までの間)の飛行に限定することとしている。 ここで、「日出から日没までの間」とは、国立天文台が発表する日の出の時刻から日の入りの時刻までの間をいうものとする。したがって、「日出」及び「日没」については、地域に応じて異なる時刻を表す。 | (5)昼間(日中)における飛行 夜間では、無人航空機の位置や姿勢だけでなく、周囲の障害物等の把握が困難になり、無人航空機の適切な制御ができず墜落等に至るおそれが高まることから、航空法第 132 条の 86 第2項第1号により、昼間(日中)」のみ(日出から日没までの間)の飛行に限定することとしている。 ここで、「日出から日没までの間」とは、国立天文台が発表する日の出の時刻から日の入りの時刻までの間をいうものとする。したがって、「日出」及び「日没」については、地域に応じて異なる時刻を表す。 |
| (6)目視の範囲内での飛行 飛行させる無人航空機の位置や姿勢を把握するとともに、その周辺に人や障害物等がないかどうか等の確認が確実に行えることを確保するため、航空法第 132 条の86 第2項第2号により、目視により常時監視を行いながらの飛行に限定することとしている。 ここで、「目視」とは、操縦者本人が自分の目で見ることをいうものとする。このため、補助者による目視は該当せず、また、飛行状況を専らモニターを用いて見ること、また双眼鏡やカメラ等を用いて見ることは、視野が限定されるため「目視」にはあたらない。 なお、安全な飛行を行うためにバッテリー残量を確認する目的等で無人航空機から一時的に目を離し、モニターを確認する等は目視飛行の範囲内とする。 操縦者が多数の無人航空機を同時運航する多数機同時運航(以下「多数機同時運航」という。)となる飛行においては、「多数機同時運航を安全に行うためのガイドライン」(令和 7年 3月制定)を参考にしつつ、無人航空機の使用者又は操縦者は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれることがないよう安全の確保を自主的に行う必要がある。 | (6)目視の範囲内での飛行 飛行させる無人航空機の位置や姿勢を把握するとともに、その周辺に人や障害物等がないかどうか等の確認が確実に行えることを確保するため、航空法第 132 条の86 第2項第2号により、目視により常時監視を行いながらの飛行に限定することとしている。 ここで、「目視」とは、無人航空機を飛行させる者本人が自分の目で見ることをいうものとする。このため、補助者による目視は該当せず、また、モニターを活用して見ること、双眼鏡やカメラ等を用いて見ることは、視野が限定されるため「目視」にはあたらない。 |
| (7)地上又は水上の人又は物件との間に一定の距離を確保した飛行 飛行させる無人航空機が地上又は水上の人又は物件と衝突することを防止するため、航空法第 132 条の 86 第2項第3号により、当該無人航空機とこれらとの間に一定の距離(30m)を確保して飛行させることとしている。 ここで、航空法第 132 条の 86 第2項第3号の規定は、飛行する無人航空機の衝突から人又は物件を保護することが趣旨であることから、一定の距離(30m)を保つべき人又は物件とは、次のとおりと解釈される。 ○「人」とは、操縦者及びその関係者(無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与している者)以外の者(第三者)をいう。 ○「物件」とは、次に掲げるもののうち、操縦者及びその関係者(無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与している者)が所有又は管理する物件以外のもの(第三者の物件)をいう。 a)中に人が存在することが想定される機器(車両等) b)建築物その他の相当の大きさを有する工作物 | (7)地上又は水上の人又は物件との間に一定の距離を確保した飛行 飛行させる無人航空機が地上又は水上の人又は物件と衝突することを防止するため、航空法第 132 条の 86 第2項第3号により、当該無人航空機とこれらとの間に一定の距離(30m)を確保して飛行させることとしている。 ここで、航空法第 132 条の 86 第2項第3号の規定は、飛行する無人航空機の衝突から人又は物件を保護することが趣旨であることから、一定の距離(30m)を保つべき人又は物件とは、次のとおりと解釈される。 ○「人」とは、無人航空機を飛行させる者及びその関係者(無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与している者)以外の者(第三者)をいう。 ○「物件」とは、次に掲げるもののうち、無人航空機を飛行させる者及びその関係者(無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与している者)が所有又は管理する物件以外のもの(第三者の物件)をいう。 a)中に人が存在することが想定される機器(車両等) b)建築物その他の相当の大きさを有する工作物 |
| 具体的な例として、次に掲げる物件が本規定の物件に該当する。 車両等:自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン 等 工作物:ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯 等 ※なお、以下の物件は、本規定の趣旨に鑑み、本規定の距離を保つべき物件には該当しない。 a)土地(田畑用地及び舗装された土地(道路の路面等)、堤防、鉄道の線路等であって土地と一体となっているものを含む。) b)自然物(樹木、雑草 等) 等 | 具体的な例として、次に掲げる物件が本規定の物件に該当する。 車両等:自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン 等 工作物:ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯 等 ※なお、以下の物件は、本規定の趣旨に鑑み、本規定の距離を保つべき物件には該当しない。 a)土地(田畑用地及び舗装された土地(道路の路面等)、堤防、鉄道の線路等であって土地と一体となっているものを含む。) b)自然物(樹木、雑草 等) 等 |
| (8)多数の者の集合する催し場所上空以外の空域での飛行 多数の者の集合する催しが行われている場所の上空においては、無人航空機を飛行させた場合に故障等により落下すれば、人に危害を及ぼす蓋然性が高いことから、航空法第 132 条の 86 第2項第4号により、一時的に多数の者が集まるような催し場所上空以外の空域での飛行に限定することとしている。 どのような場合が「多数の者の集合する催し」に該当するかについては、催し場所上空において無人航空機が落下することにより地上の人に危害を及ぼすことを防止するという趣旨に照らし、集合する者の人数や密度だけでなく、特定の場所や日時に開催されるものかどうか、また、主催者の意図等も勘案して総合的に判断される。 なお、飛行許可・承認の取得の有無によらず、飛行予定経路下において想定して いない「多数の者の集合する催し」が開催されることが明らかになり、飛行場所に第三者の立ち入り又はそのおそれのあることを確認したときは、直ちに当該無人航空機の飛行を停止し、飛行経路の変更、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがない場所への着陸その他の必要な措置を講じなければならない。 | (8)多数の者の集合する催し場所上空以外の空域での飛行 多数の者の集合する催しが行われている場所の上空においては、無人航空機を飛行させた場合に故障等により落下すれば、人に危害を及ぼす蓋然性が高いことから、航空法第 132 条の 86 第2項第4号により、一時的に多数の者が集まるような催し場所上空以外の空域での飛行に限定することとしている。 どのような場合が「多数の者の集合する催し」に該当するかについては、催し場所上空において無人航空機が落下することにより地上の人に危害を及ぼすことを防止するという趣旨に照らし、集合する者の人数や密度だけでなく、特定の場所や日時に開催されるものかどうか、また、主催者の意図等も勘案して総合的に判断される。 |
| 具体的な事例は次のとおりである。 ○該当する例: 航空法第 132 条の 86 第2項第4号に明示されている祭礼、縁日、展示会のほか、プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催されるコンサート等のイベント、ドローンショー(自社敷地内、無人の競技場内 等、第三者の立入管理措置が行われていることが明白である場所での事前練習や企業向けの配信用撮影等を除く)、花火大会、盆踊り大会、マラソン、街頭パレード、選挙等における屋外演説会、デモ(示威行為) 等 | 具体的な事例は次のとおりである。 ○該当する例: 航空法第 132 条の 86 第2項第4号に明示されている祭礼、縁日、展示会のほか、プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催されるコンサート、町内会の盆踊り大会、デモ(示威行為) 等 |
| ○該当しない例: 6.第三者に関すること に示す関与者のみが参加する催し場所上空の飛行、自然発生的なもの(例えば、混雑による人混み、信号待ち) 等 なお、飛行の形態はケース毎に異なることから、上記において多数の者の集合する催しに該当しない場合であっても、特定の時間、特定の場所に数十人が集合しているときには「多数の者の集合する催し」に該当する可能性がある。 | ○該当しない例: 自然発生的なもの(例えば、混雑による人混み、信号待ち 等) なお、上記に該当しない場合であっても、特定の時間、特定の場所に数十人が集合している場合には「多数の者の集合する催し」に該当する可能性がある。 |
| (9)危険物の輸送の禁止 無人航空機には、既に数 kg~10kg の物件を輸送する能力を有するものもあり、火薬類、高圧ガス、引火性液体等の危険物を輸送することが十分に可能であるところ、これらの物件を輸送する無人航空機が墜落した場合や輸送中にこれらの物件が漏出した場合には、周囲への当該物質の飛散や機体の爆発により、人への危害や他の物件への損傷が発生するおそれがあるため、航空法第 132 条の 86 第2項第5号により、危険物の輸送を禁止することとしている。 無人航空機による輸送を禁止する危険物については、航空法施行規則第 236 条の80 及び「無人航空機による輸送を禁止する物件等を定める告示」(平成 27 年 11 月17 日付国土交通省告示第 1142 号)において定められている。 なお、当該飛行に必要不可欠であり、飛行中、常に機体と一体となって輸送される等の物件は、航空法施行規則第 236 条の 80 第2項における無人航空機の飛行のために輸送する物件として、輸送が禁止される物件に含まれないものとする。 具体的には次に掲げる物件が該当する。 ・無人航空機の飛行のために必要な燃料や電池 ・業務用機器(カメラ等)に用いられる電池 ・安全装備としてのパラシュートを開傘するために必要な火薬類や高圧ガス 等 | (9)危険物の輸送の禁止 無人航空機には、既に数 kg~10kg の物件を輸送する能力を有するものもあり、火薬類、高圧ガス、引火性液体等の危険物を輸送することが十分に可能であるところ、これらの物件を輸送する無人航空機が墜落した場合や輸送中にこれらの物件が漏出した場合には、周囲への当該物質の飛散や機体の爆発により、人への危害や他の物件への損傷が発生するおそれがあるため、航空法第 132 条の 86 第2項第5号により、危険物の輸送を禁止することとしている。 無人航空機による輸送を禁止する危険物については、航空法施行規則第 236 条の80 及び「無人航空機による輸送を禁止する物件等を定める告示」(平成 27 年 11 月17 日付国土交通省告示第 1142 号)において定められている。 なお、当該飛行に必要不可欠であり、飛行中、常に機体と一体となって輸送される等の物件は、航空法施行規則第 236 条の 80 第2項における無人航空機の飛行のために輸送する物件として、輸送が禁止される物件に含まれないものとする。 具体的には次に掲げる物件が該当する。 ・無人航空機の飛行のために必要な燃料や電池 ・業務用機器(カメラ等)に用いられる電池 ・安全装備としてのパラシュートを開傘するために必要な火薬類や高圧ガス 等 |
| (10)物件投下の禁止 飛行中に無人航空機から物件を投下した場合には、地上の人等に危害をもたらすおそれがあるとともに、物件投下により機体のバランスを崩すなど無人航空機の適切な制御に支障をきたすおそれもあるため、航空法第 132 条の 86 第2項第6号により、物件投下を禁止することとしたものである。 ここで、水や農薬等の液体を散布する行為は物件投下に該当し、対象物件を地表 等に落下させることなく地上の人員に受け渡す行為や輸送した物件を地表に置く行為は物件投下には該当しない。 | (10)物件投下の禁止 飛行中に無人航空機から物件を投下した場合には、地上の人等に危害をもたらすおそれがあるとともに、物件投下により機体のバランスを崩すなど無人航空機の適切な制御に支障をきたすおそれもあるため、航空法第 132 条の 86 第2項第6号により、物件投下を禁止することとしたものである。 ここで、水や農薬等の液体を散布する行為は物件投下に該当し、輸送した物件を地表に置く行為は物件投下には該当しない。 |
| 4.条件を満たすことにより許可・承認が不要となる飛行 十分な強度を有する紐等(長さ 30m以内)で地表又は固定物に係留することにより、紐等の長さの範囲外に無人航空機が飛行することを物理的に防止できることから、以下の個別の許可・承認が不要となる。 ・人口集中地区上空における飛行 (法第 132 条の 85 第1項第2号) ・夜間飛行 (法第 132 条の 86 第2項第1号) ・目視外飛行 (法第 132 条の 86 第2項第2号) ・第三者から 30m 以内の飛行 (法第 132 条の 86 第2項第3号) ・物件投下 (法第 132 条の 86 第2項第6号) 特に、危険物に該当する農薬の空中散布には、引き続き危険物輸送のための飛行の承認(法第 132 条の 86 第2項第5号)が必要である。 航空法施行規則第 236 条の 76 第4号に定められた補助者の配置その他の係留することにより無人航空機の飛行を制限した範囲内において第三者の立入りを管理する措置等についての具体的な例は、補助者による監視及び口頭警告並びに関係者以外の立ち入りを制限する旨の看板やコーン等による表示などがある。加えて、不測の事態に備え、無人航空機、係留地点、立入りを管理する措置を講じた外縁等に、操縦者と常に連絡の取れる連絡先を明示すること。また、トラブルの未然防止のため、必要に応じて周囲の理解を得るよう努めるなど、円滑に運用するための活動を実施すること。 立入を管理するために講じた措置等が機能せず、無人航空機の下に人の立入り又はそのおそれのあることを確認したときは、直ちに当該無人航空機の飛行を停止し、飛行経路の変更、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがない場所への着陸その他の必要な措置を講じなければならない。また、立入制限が機能しない場合は、航空法施行規則第 236 条の 76 第4号の措置を適切に講じているとは認められないため、係留をしていたとしても、飛行させる空域・方法により必要な許可・承認がなければ、飛行させることはできない。 物件等に沿って配置する主索やガイドレール等と、無人航空機を繋ぐ連結索により係留される場合、飛行範囲が物件から 30m 以内に物理的に制限されるため、その趣旨に照らして係留と認められる。この場合に、30m の上限規定は連結索のみに適用される。なお、連結索の長さによらず、主索をたわませる等により無人航空機が物件から 30m 以上離れることがあってはならない。 車両、航空機等に連結索を固定するものは、えい航であり、一般に係留とは認められない。 航空法施行規則第 236 条の6第2項第2号に掲げる飛行(十分な強度を有する紐等(長さが三十メートル以下のものに限る。)で係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行)も、本項により解釈される。 | 4.条件を満たすことにより許可・承認が不要となる飛行 十分な強度を有する紐等(長さ 30m以内)で地表又は固定物に係留することにより、紐等の長さの範囲外に無人航空機が飛行することを物理的に防止できることから、以下の個別の許可・承認が不要となる。 ・人口集中地区上空における飛行 (法第 132 条の 85 第1項第2号) ・夜間飛行 (法第 132 条の 86 第2項第1号) ・目視外飛行 (法第 132 条の 86 第2項第2号) ・第三者から 30m 以内の飛行 (法第 132 条の 86 第2項第3号) ・物件投下 (法第 132 条の 86 第2項第6号) 特に、危険物に該当する農薬の空中散布には、引き続き危険物輸送のための飛行の承認(法第 132 条の 86 第2項第5号)が必要である。 航空法施行規則第 236 条の 76 第4号に定められた補助者の配置その他の係留することにより無人航空機の飛行を制限した範囲内において第三者の立入りを管理する措置等についての具体的な例は、補助者による監視及び口頭警告並びに関係者以外の立ち入りを制限する旨の看板やコーン等による表示などがある。加えて、不測の事態に備え、無人航空機、係留地点、立入りを管理する措置を講じた外縁等に、操縦者と常に連絡の取れる連絡先を明示すること。また、トラブルの未然防止のため、必要に応じて周囲の理解を得るよう努めるなど、円滑に運用するための活動を実施すること。 立入を管理するために講じた措置等が機能せず、無人航空機の下に人の立入り又はそのおそれのあることを確認したときは、直ちに当該無人航空機の飛行を停止し、飛行経路の変更、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがない場所への着陸その他の必要な措置を講じなければならない。また、立入制限が機能しない場合は、航空法施行規則第 236 条の 76 第4号の措置を適切に講じているとは認められないため、係留をしていたとしても、飛行させる空域・方法により必要な許可・承認がなければ、飛行させることはできない。 物件等に沿って配置する主索やガイドレール等と、無人航空機を繋ぐ連結索により係留される場合、飛行範囲が物件から 30m 以内に物理的に制限されるため、その趣旨に照らして係留と認められる。この場合に、30m の上限規定は連結索のみに適用される。なお、連結索の長さによらず、主索をたわませる等により無人航空機が物件から 30m 以上離れることがあってはならない。 車両、航空機等に連結索を固定するものは、えい航であり、一般に係留とは認められない。 航空法施行規則第 236 条の6第2項第2号に掲げる飛行(十分な強度を有する紐等(長さが三十メートル以下のものに限る。)で係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行)も、本項により解釈される。 |
| 5.立入管理措置に関すること 航空法第 132 条の 85 第1項では、「立入管理措置は、無人航空機の飛行経路下において操縦者及びこれを補助する者以外の立入りを管理する措置であって国土交通省令で定めるもの」としており、航空法施行規則第 236 条の 70 においてその詳細として「補助者の配置、立入りを制限する区画の設定その他の適切な措置」としている。補助者の役割については、例として監視及び口頭警告などがあり、また、第三者の立入りを制限する区画(立入管理区画)の設定については、飛行させる無人航空機の落下分散範囲も考慮しなければならないところ、当該区画の範囲を明示するために必要な標識の設置等が必要となるが、関係者以外の立入りを制限する旨の看板、コーン等による表示などの措置が必要となる。なお、無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)(平成 27 年 11 月 17 日制定 国空航第 684 号、国空機第 923号、以下「審査要領」という。)5-4(1)d)ウ)(iii)に基づき、機体に取り付けられたカメラを活用して補助者を配置せずに目視外飛行を行う場合(技能証明を有する者が機体認証を受けた機体を飛行させる場合であって、国土交通大臣の承認を受けずに同等の飛行を行う場合を含む。)にあっては、機体に取り付けられたカメラにより進行方向の飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立ち入りが無いことを確認することを以て、立入管理措置が行われているものとみなす。 | 5.立入管理措置に関すること 航空法第 132 条の 85 第1項では、「立入管理措置は、無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の立入りを管理する措置であって国土交通省令で定めるもの」としており、航空法施行規則第 236 条の 70 においてその詳細として「補助者の配置、立入りを制限する区画の設定その他の適切な措置」としている。補助者の役割については、例として監視及び口頭警告などがあり、また、第三者の立入りを制限する区画(立入管理区画)の設定については、当該区画の範囲を明示するために必要な標識の設置等が必要となるが、関係者以外の立入りを制限する旨の看板、コーン等による表示などの措置が必要となる。 |
| 6.第三者に関すること (1)「第三者」について 航空法 132 条の 87 などで規定する「第三者」の定義については、以下のとおり。 「第三者」とは、無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与していない者をいう。次に掲げる者は無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与しており、「第三者」には該当しない。 ①無人航空機の飛行に直接的に関与している者 直接的に関与している者(以下「直接関与者」という。)とは、操縦者、現に操縦はしていないが操縦する可能性のある者、補助者等無人航空機の飛行の安全確保に必要な要員とする。 ②無人航空機の飛行に間接的に関与している者 間接的に関与している者(以下「間接関与者」という。)とは、飛行目的について操縦者と共通の認識を持ち、次のいずれにも該当する者とする。 a)操縦者が、間接関与者について無人航空機の飛行の目的の全部又は一部に関与していると判断している。 b)間接関与者が、操縦者から、無人航空機が計画外の挙動を示した場合に従うべき明確な指示と安全上の注意を受けている。なお、間接関与者は当該指示と安全上の注意に従うことが期待され、操縦者は、指示と安全上の注意が適切に理解されていることを確認する必要がある。 c)間接関与者が、無人航空機の飛行目的の全部又は一部に関与するかどうかを自ら決定することができる。 例:映画の空撮における俳優やスタッフ、学校等での人文字の空撮における生徒 等 | 6.第三者に関すること 航空法 132 条の 87 などで規定する「第三者」の定義については、以下のとおり。 「第三者」とは、無人航空機の飛行に直接又は間接的に関与していない者をいう。次に掲げる者は無人航空機の飛行に直接又は間接的に関与しており、「第三者」には該当しない。 (a)無人航空機の飛行に直接関与している者 直接関与している者とは、操縦者、現に操縦はしていないが操縦する可能性のある者、補助者等無人航空機の飛行の安全確保に必要な要員とする。 (b)無人航空機の飛行に間接的に関与している者 間接的に関与している者(以下「間接関与者」という。)とは、飛行目的について無人航空機を飛行させる者と共通の認識を持ち、次のいずれにも該当する者とする。 a. 無人航空機を飛行させる者が、間接関与者について無人航空機の飛行の目的の全部又は一部に関与していると判断している。 b. 間接関与者が、無人航空機を飛行させる者から、無人航空機が計画外の挙動を示した場合に従うべき明確な指示と安全上の注意を受けている。なお、間接関与者は当該指示と安全上の注意に従うことが期待され、無人航空機を飛行させる者は、指示と安全上の注意が適切に理解されていることを確認する必要がある。 c. 間接関与者が、無人航空機の飛行目的の全部又は一部に関与するかどうかを自ら決定することができる。 |
| (2)「第三者上空」について 「第三者上空」とは、(1)の「第三者」の上空をいい、当該第三者が乗り込んでいる移動中の車両等(3.(7)に例示する車両等をいう。以下同じ。)の上空を含むものとする。この場合の「上空」とは、「第三者」の直上だけでなく、飛行させる無人航空機の落下距離(飛行範囲の外周から製造者等が保証した落下距離)を踏まえ、当該無人航空機が落下する可能性のある領域に第三者が存在する場合は、当該無人航空機は当該第三者の上空にあるものとみなす。 また、無人航空機の飛行が終了するまでの間、無人航空機の飛行に関与しない者((1)の「第三者」)の態様及び飛行の形態が以下のいずれかに該当する場合は、無人航空機が第三者上空にあるとはみなさないこととする。 ①「第三者」が遮蔽物に覆われており、当該遮蔽物に無人航空機が衝突した際に当 該第三者が保護される状況にある場合(当該第三者が屋内又は車両等(移動中のものを除く。)の内部にある場合等。) ②「第三者」が、移動中の車両等(無人航空機が当該車両等に衝突した際に当該第三者が保護される状況にある場合に限る。)の中にある場合であって、無人航空機が必要な要件を満たした上で審査要領5-4(3)c)カ)(iii)に規定されるレベル 3.5 飛行として一時的に当該移動中の車両等の上空を飛行するとき。 ただし、「第三者」が遮蔽物に覆われず、無人航空機の衝突から保護されていない状況になった場合には、無人航空機が「第三者上空」にあるとみなされる点に留意すること。 | |
| (3)「第三者が立ち入った場合の措置」について (2)②により無人航空機が一時的に移動中の車両等の上空を横断する場合(「第三者」が当該車両等に保護されていない状況となった場合を除く。)については、航空法第 132 条の 87 で規定する「特定飛行中の無人航空機の下に人の立入り又はそのおそれのあることを確認したとき」に該当しない。 | |
| 7.補助者の役割等に関すること 航空法施行規則第 236 条の 75 に規定する補助者の役割等については、前提として、操縦者は機体の動きや操縦に集中する必要があり、離着陸エリアを含めた飛行経路の管理を操縦と同時に行うことが困難であるため、飛行準備や飛行経路の安全管理、第三者の立入り管理などは補助者が主として行う必要がある。補助者は、離着陸場所や飛行経路周辺の地上や空域の安全確認を行うほか、飛行前の事前確認で明らかになった障害物等の対処について手順に従い作業を行うことに加え、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視すること。 操縦者とのコミュニケーションは予め決められた手段を用いて行い、危険予知の警告や緊急着陸地点への誘導、着陸後の機体回収や安全点検の補助も行うこと。 無人航空機の飛行経路や範囲に応じ補助者の数や配置、各人の担当範囲や役割、異常運航時の対応方法も決めておく必要がある。 | 7.補助者の役割等に関すること 航空法施行規則第 236 条の 75 に規定する補助者の役割等については、前提として、無人航空機を飛行させる操縦者は機体の動きや操縦に集中する必要があり、離着陸エリアを含めた飛行経路の管理を操縦と同時に行うことが困難であるため、飛行準備や飛行経路の安全管理、第三者の立入り管理などは補助者が主として行う必要がある。補助者は、離着陸場所や飛行経路周辺の地上や空域の安全確認を行うほか、飛行前の事前確認で明らかになった障害物等の対処について手順に従い作業を行うこと。 操縦者とのコミュニケーションは予め決められた手段を用いて行い、危険予知の警告や緊急着陸地点への誘導、着陸後の機体回収や安全点検の補助も行うこと。 無人航空機の飛行経路や範囲に応じ補助者の数や配置、各人の担当範囲や役割、異常運航時の対応方法も決めておく必要がある。 |
| 8.捜索、救助等のための特例 航空法第 132 条の 92 は、事故や災害等の発生時における人命の捜索、救助等が極めて緊急性が高く、かつ、公共性の高い行為であることから、当該捜索、救助等に支障が出ないよう、航空法第 132 条の 85 による無人航空機の飛行の禁止空域に関する規定や航空法第 132 条の 86 による飛行の方法に関する規定などの適用を除外することにより、捜索又は救助等の迅速化を図ることを趣旨としたものである。 本特例については、航空法施行規則第 236 条の 88 により、以下の者に対して適用される。 ・国又は地方公共団体 ・国又は地方公共団体の依頼により捜索又は救助を行う者 また、国土交通省令で定める目的については、航空法施行規則第 236 条の 89 により、「捜索又は救助」と定められているが、本規定における「捜索又は救助」とは、事故や災害の発生等に際して人命や財産に急迫した危難のおそれがある場合において、人命の危機又は財産の損傷を回避するための措置(調査・点検、捜査等の実施を含む。)を指しており、当該措置をとることについて緊急性がある(※ (※ 特に大規模災害発生時においては、多数の道路の寸断や集落の孤立が発生する可能性があることから、被災地の孤立地域等への医薬品、衛生用品、食料品、飲料水等の生活必需品の輸送、危険を伴う箇所での調査・点検のほか、住民避難後の住宅やその地域の防犯対策のための無人航空機の飛行も含め、人命の危機又は財産の損傷を回避するための措置として、航空法第132 条の92 に該当する飛行として取り扱うものとする。 なお、特例の対象となる飛行においても、飛行の安全性を確保することは言うまでもないことから、「航空法第 132 条の 92 の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン」(平成 27 年 11 月 17 日付国空航第 687 号、国空機第 926 号)を参考にしつつ、無人航空機の使用者又は操縦者は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれることがないよう安全の確保を自主的に行う必要がある。 | 8.捜索、救助等のための特例 航空法第 132 条の 92 は、事故や災害等の発生時における人命の捜索、救助等が極めて緊急性が高く、かつ、公共性の高い行為であることから、当該捜索、救助等に支障が出ないよう、航空法第 132 条の 85 による無人航空機の飛行の禁止空域に関する規定や航空法第 132 条の 86 による飛行の方法に関する規定などの適用を除外することにより、捜索又は救助等の迅速化を図ることを趣旨としたものである。 本特例については、航空法施行規則第 236 条の 88 により、以下の者に対して適用される。 (1)国又は地方公共団体 (2)国又は地方公共団体の依頼により捜索又は救助を行う者 また、国土交通省令で定める目的については、航空法施行規則第 236 条の 89 により、「捜索又は救助」と定められているが、本規定における「捜索又は救助」とは、事故や災害の発生等に際して人命や財産に急迫した危難のおそれがある場合において、人命の危機又は財産の損傷を回避するための措置(調査・点検、捜査等の実施を含む。)を指しており、当該措置を目的として無人航空機を飛行させる場合については、本特例が適用されることとなる。 なお、特例の対象となる飛行においても、飛行の安全性を確保することは言うまでもないことから、「航空法第 132 条の 92 の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン」(平成 27 年 11 月 17 日付国空航第 687 号、国空機第 926 号)を参考にしつつ、無人航空機の使用者又は飛行させる者は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれることがないよう安全の確保を自主的に行う必要がある。 |
| 9.屋内での無人航空機の飛行 建物内等の屋内での飛行については、航空法上の各規制は適用されない。ここで、(1)及び(2)の空間内の飛行は屋内での飛行であると見なし、(3)の行為は屋外での飛行とは見なさない。屋内での飛行経路が開口部に接近する場合には、無人航空機が屋内から屋外へ意図せず飛び出すことを抑止するために必要な措置を講じること。予定の経路を逸脱して屋外に飛び出してしまった場合には、直ちに飛行を終了するか、速やかに屋内に引き返すための措置を講じること。 屋外を飛行するために必要な飛行許可承認の手続きを実施せず屋外を飛行させた場合、航空法等違反となる可能性があることに十分留意すること。 (1)開口部はあるが、内部と外部が明確に区別された空間 例:トンネル内部、地下道内部、煙突内部、窓・扉の開いた建物等 (2)無人航空機のスケールより目の細かいネット、金網等で囲われ、無人航空機が飛行範囲を逸脱することがないように措置された空間 (3)開口部付近において、飛行前の挙動確認のために一度操縦者の近くで低高度の浮上を実施し、これに引き続き空間内部に向けて直ちに進入する行為 | 9.屋内での無人航空機の飛行 建物内等の屋内での飛行については、航空法上の各規制は適用されない。ここで、(1)及び(2)の空間内の飛行は屋内での飛行であると見なし、(3)の行為は屋外での飛行とは見なさない。屋内での飛行経路が開口部に接近する場合には、無人航空機が屋内から屋外へ意図せず飛び出すことを抑止するために必要な措置を講じること。予定の経路を逸脱して屋外に飛び出してしまった場合には、直ちに飛行を終了するか、速やかに屋内に引き返すための措置を講じること。 屋外を飛行するために必要な飛行許可承認の手続きを実施せず屋外を飛行させた場合、航空法等違反となる可能性があることに十分留意すること。 (1)開口部はあるが、内部と外部が明確に区別された空間 例:トンネル内部、地下道内部、煙突内部、窓・扉の開いた建物等 (2)無人航空機のスケールより目の細かいネット、金網等で囲われ、無人航空機が飛行範囲を逸脱することがないように措置された空間 (3)開口部付近において、飛行前の挙動確認のために一度飛行させる者の近くで低高度の浮上を実施し、これに引き続き空間内部に向けて直ちに進入する行為 |
まとめ
2024年6月の改正は、それまでの「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」を作成した以降に対外公表したものや、制度改正を踏まえたものが反映されています。
また、催し場所上空の判断や、物流での受け渡し方法、能登半島地震対応を踏まえたと思われる捜索救助の緊急性の判断など、国交省が行政運営をしていく中で明確にしておくべきと考えた中身も反映されたものだと認識しています。

このウェブサイトに掲載している情報の正確性には細心の注意を払っております。しかしながら法令解釈や制度改正等で不正確な表記を含む場合があり得ます。掲載情報を用いた行為によって生じた損害には一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
行政書士さいれんじ事務所はドローン飛行許可申請を代行しています。
ドローンの飛行許可申請に関するご依頼は、お気軽にお問い合わせください。
プロフェッショナルな行政書士がお手続きを代行しスムーズに許可を取得。そしてドローン飛行を法的にサポートいたします。


